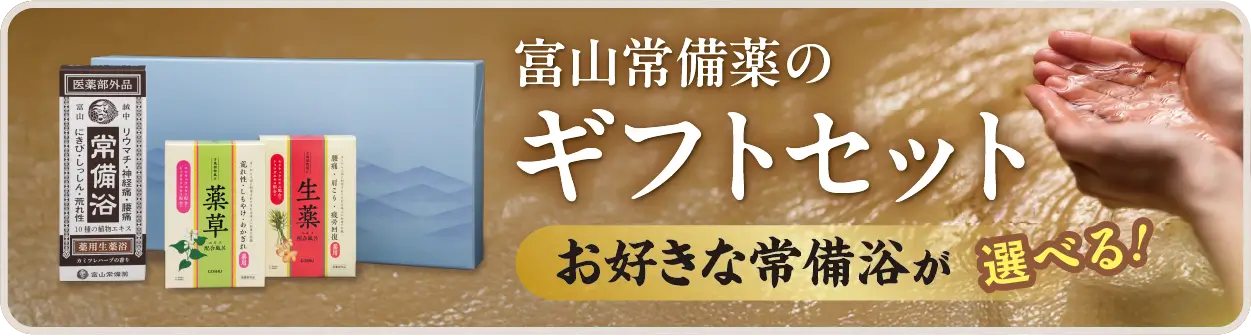甘くみないで!
「乾燥」は健康の大敵
じつは深刻 乾燥が疾患の原因に!
冬になるとよく耳にする「乾燥注意報」。
大気の乾燥により火災などが発生する危険が大きいと予想される場合に発表されるものですが、体にとっても乾燥は注意すべき事態です。
その主なものが、「健康リスクの増加」です。
空気が乾燥すると菌やウイルスの増殖力が高くなり、健康リスクが増加します。
具体的には、乾燥によって粘膜が傷ついたりバリア機能が低下すると、ウイルスや細菌が体内に侵入しやすくなり、風邪やウイルス性疾患の原因になるのです。
乾燥とは、一般的に湿度40%を下回る状態とされています。
現代では夏もエアコンなどにより室内が乾燥しており、冬に限らず一年を通して対策が必要なことも少なくありません。
乾燥対策を始める前には、必ず自分の部屋の湿度を確認しましょう。
室内の湿度の目安は40~60%。
むやみに室内の湿度を上げると、カビやダニが発生しやすくなってしまいます。
湿度調整には加湿器が便利です。
しかし、室内に洗濯物や濡れたタオルを干すなど、ちょっとした工夫で加湿はできます。

部位ごとのケアと規則正しい生活で改善を
乾燥から身を守るためには、室内の湿度調整のほか、ケアを行うことも重要です。
主な部位ごとに症状と対策方法をまとめると、
○肌
乾燥肌は、「ただの肌あれ」と軽く考えられがちですが、水分や皮脂が不足しているサイン。
かゆみや湿疹を伴うことが多く、パサつきやガサガサの感触が特徴。
ひび割れや粉ふきとなど、見た目も変化しウイルスやアレルギー物質が体内に入る原因になります。
入浴後や洗顔後に肌がつっぱるような感覚がある人も乾燥肌を疑ってみましょう。
基本的な対策は、化粧水や乳液、クリームなどでうるおいを与えること。
洗った後は、タオルを押し当てるようにして水分をやさしく拭き取ることもポイント。
外出する際は日焼け止めクリームを塗って、バリア機能の低下を招く紫外線に注意しましょう。

○目
表面に溜まる涙が通常以上に蒸発してうるおいが保てなくなり、まばたきをしても目が乾いてしまうことが続くと、ドライアイ発症の原因になります。
こまめに目薬をさし、意識的にまばたきの回数を増やしましょう。
そのほか、蒸しタオルを目に当てて血流を促進することも乾燥の改善に効果的です。
○頭皮
乾燥により角質がはがれやすくなり、頭皮の水分が蒸発して乾燥が進みます。乾燥するとかゆみを感じてかきむしるため、フケが増えてしまいます。
すぐにできる対策は、指の腹でマッサージするように洗い、しっかりすすいでシャンプーの洗い残しがないようにすること。
乾燥肌用のシャンプーを使うのもおすすめです。
フケを気にしてシャンプーの回数を増やしたり、爪を立ててゴシゴシ洗うと頭皮に負担がかかり逆効果となるので避けましょう。
これらに加えてもうひとつ気をつけたいことがあります。
それは、規則正しい生活を心がけること。
体の乾燥を予防するには、ターンオーバーと呼ばれる皮膚細胞の新陳代謝が正常に行われていることが重要です。
しかし、偏った食事や睡眠不足、血行不良などでその周期が乱れることでも体の乾燥は起こるのです。
保湿などの対策と併せて日々の習慣を見直し、乾燥の改善と予防をして元気にすごしましょう。