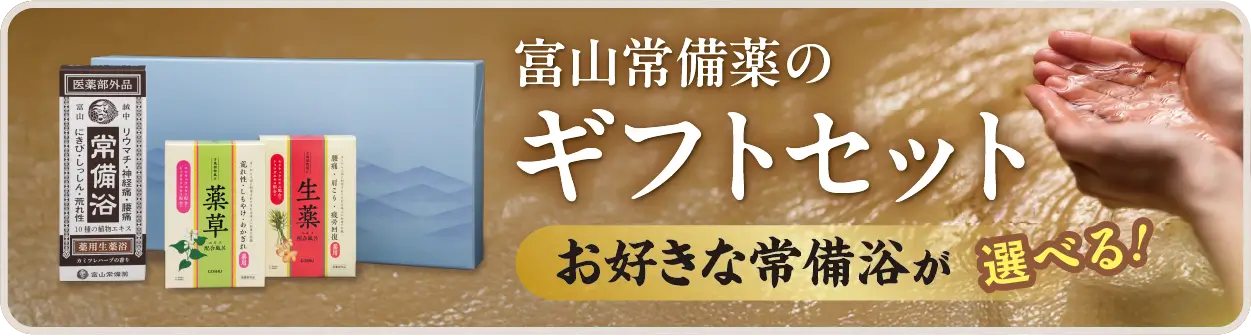「細菌」や「ウイルス」が原因の食中毒を防ぐ!
薬剤師 なお
とても楽しい家族のだんらんの場である食卓、平凡に何事もなく毎日の日常として過ぎていけばとてもいいのですが、腹痛や下痢、おう吐など食中毒かなと思われるような症状が現れると、せっかくの食卓が台無しになります。
食中毒を引き起こす主な原因は、「細菌」や「ウイルス」などの微生物です。
 「細菌」は、温度と湿度の条件がそろうと食べ物の中で増殖し、菌の数が一定以上になったものを食べると食中毒を引き起こします。ちょうど高温多湿の夏場が「細菌」にとっては最適の環境となります。
「細菌」は、温度と湿度の条件がそろうと食べ物の中で増殖し、菌の数が一定以上になったものを食べると食中毒を引き起こします。ちょうど高温多湿の夏場が「細菌」にとっては最適の環境となります。
一方、「ウイルス」は、食べ物の中では増殖しませんが、ヒトの身体の中に入ってから増殖し、食中毒を引き起こします。低温や乾燥の中でも長く生存するため、冬場に起こりやすい食中毒です。
「細菌」の大きさは1~10μm(1μmは1mmの1/1000)、「ウイルス」の大きさは、さらに小さく「細菌」の1/1000ぐらいの大きさで、両方とも顕微鏡を使用しないと見えない大きさです。そんな目に見えないものの悪さを防ぐことができないのでは?とお思いになるかもしれませんが、意外と簡単に防ぐことができるのです。そのポイントを紹介します。
「細菌」による食中毒を防ぐには、①「細菌」を食べ物に付けない。②食べ物についた「細菌」を増やさない。③食べ物や調理器具についた「細菌」をやっつける。の3つの原則があります。
「ウイルス」による食中毒を防ぐには、①「ウイルス」を台所に持ち込まない。②仮に持ち込んでも「ウイルス」をひろげない。③食べ物に「ウイルス」をつけない。④付着してしまった「ウイルス」を加熱してやっつける。の4つの原則があります。
そんな食中毒を防ぐ原則を守るために、具体的にどのようにしたら家庭での食中毒を防ぐことができるかが、次の6つのポイントです。

◎ポイント1 買い物
・生鮮商品は新鮮なものを購入する。
・消費期限を確認する。
・肉や魚は汁が他の食品につかないようビニールに入れる。
・温度管理が必要な食品は最後に購入し、買い物をしたら早めに帰る。
◎ポイント2 家庭での保存
・温度管理が必要なものは、速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。
・肉や魚は汁が他の食品につかないよう保管する。
・冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持し、詰めすぎない。
・肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手を洗う。
◎ポイント3 下準備
・調理の前には手を洗う。
・生の肉、魚、卵などを取扱った後は手を洗う。
・生の肉や魚を切った後、包丁やまな板はしっかり洗う。
・包丁やまな板は肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて使い分ける。
・ラップしてある野菜、カット野菜も流水できれいに洗う。
・冷凍食品の解凍は、必要な分だけ、冷蔵庫や電子レンジで行う。
・使用後のふきんやタオル、調理器具は熱湯や漂白剤などで消毒する。
◎ポイント4 調理
・加熱して調理する食品は十分加熱する。※中心部の温度:75℃,1分以上
◎ポイント5 食事
・食べる前に石けんで手を洗う。
・清潔な食器を使う。
・作った料理は、長時間放置しない。
◎ポイント6 残った食品
・残った食品を扱う前にも手を洗い、清潔な容器に保存する。
・温めなおすときも十分加熱する。
・ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てる。
こんな簡単なこれら6つのポイントをしっかり守り、皆さんには健康で明るい食生活を送っていただきたいと富山常備薬社員一同願っております。
それでも、もし、お腹が痛くなったり、下痢をしたり、吐き気などの症状が出て、食中毒かな?と思われたら、早めにお医者さんを受診されることをおすすめします。
(参考文献)
●厚生労働省.食中毒.食中毒|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
●政府広報オンライン.食中毒予防の原則と6つのポイント.2025年7月11日,食中毒予防の原則と6つのポイント|政府広報オンライン (gov-online.go.jp)