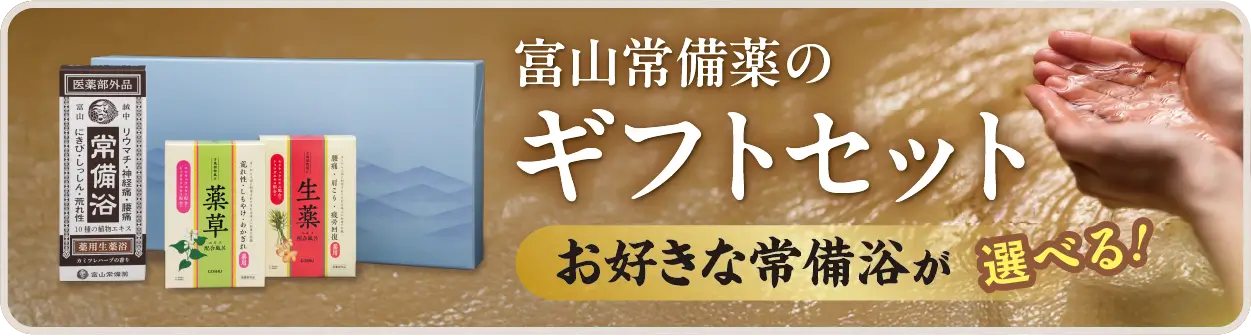皮膚をターゲットとする薬
ー未病・ウェルビーイングの視点から考える皮膚薬ー
~くすりを知るシリーズ⑬~
薬剤師 NK
はじめに
皮膚は、私たちの体全体を覆う最大の臓器であり、成人の場合、体表面積の約15~16%を占めると言われています。皮膚は単なる体の覆いではなく、身体を守る重要なバリア機能を持ち、健康状態を反映する鏡とも言えます。
皮膚の状態が良好であることは、単に病気を防ぐだけでなく、心身のウェルビーイングにも深く関わっています。
本コラムでは、皮膚をターゲットとする薬の歴史・進化・未来に加え、未病やウェルビーイングの観点からその意義を考察します。
1. 皮膚薬の重要性と多様な役割
皮膚薬は、単なる外用薬にとどまらず、実に多様な役割を果たしています。たとえば、アトピー性皮膚炎や乾癬、ニキビといった慢性的な皮膚疾患に対しては、ステロイド(リンデロンV®[ベタメタゾン吉草酸エステル]、ロコイド®[ヒドロコルチゾン酪酸エステル])や免疫抑制剤(プロトピック®[タクロリムス])、さらには最近では生物学的製剤(デュピクセント®[デュピルマブ]、コセンティクス®[セクキヌマブ]など)が使用されています。
また、細菌や真菌、ウイルスによる感染症に対しては、抗生物質(フシジン酸製剤:フシジンレオ®、ナジフロキサシン製剤:アクアチム®)、抗真菌薬(ラミシール®[テルビナフィン]、ルリコン®[ルリコナゾール])、抗ウイルス薬(ゾビラックス®[アシクロビル]など)が外用・内服の形で処方されます。
さらに、創傷治癒や皮膚再生の分野では、ヒアルロン酸(ヒアレイン®)や成長因子(フィブラストスプレー®[トラフェルミン])を組み合わせた創傷被覆材、銀を含む創傷被覆材(アクアセルAg®)が開発されており、皮膚の回復を促します。加えて、皮膚を薬剤の吸収経路とする経皮吸収型薬剤(フェンタニルパッチ製剤:デュロテップ®、ホルモンパッチ製剤:ル・エストロジェル®、ニコチンパッチ:ニコチネルTTS®など)は、全身への作用を目指した応用例です。
最近では、美容や美白※1およびアンチエイジングの観点から、トレチノイン(ベサノイドカプセル®)、ビタミンC誘導体(アスコルビン酸リン酸Mgなど)、美白成分(ハイドロキノン、トラネキサム酸を含む医療用外用薬及び内服薬)が注目されています。
このように、皮膚薬は病気の治療のみならず、予防や健康維持、さらには生活の質の向上といった幅広い役割を担っています。
※1:美白:皮膚の色素沈着を抑制し、明るく透明感のある肌を保つためのスキンケアおよび薬剤の概念。主にメラニン生成抑制を目的とする。
2. 皮膚薬の歴史と進化

皮膚薬の歴史は古く、自然由来の成分から始まりました。古代の人々はハーブやミツロウ、オリーブオイルなどを皮膚のトラブルに利用しており、アーユルヴェーダや中医学ではウコン、カンフル、アロエなどが頻繁に用いられてきました。近代に入り、消毒薬や硫黄、タールなどの有効成分が医療に取り入れられ、さらに20世紀後半にはステロイド外用薬や抗生物質の外用剤が登場し、皮膚薬の選択肢が大きく広がりました。
現代では、生物学的製剤の登場により、従来の治療法に反応しない乾癬やアトピー性皮膚炎の患者にも新たな可能性が提供されています。たとえば、IL-4、IL-13、IL-17などのインターロイキンを標的とする薬剤(例:デュピクセント®、コセンティクス®)は、炎症のメカニズムに直接作用し、高い治療効果を示しています。加えて、JAK阻害薬(オルミエント®[バリシチニブ]、コレクチム®軟膏[デルゴシチニブ])は内服に加え、外用剤としても開発が進んでおり、より局所的な治療が可能になっています。
さらに、ナノテクノロジーやマイクロニードルといった技術革新も進んでおり、薬剤を皮膚の深層へ効率的に届ける新たな方法として注目されています。これにより、皮膚薬の精度と安全性は大きく向上してきました。
3. 皮膚薬と未病・ウェルビーイング
皮膚は単なる臓器ではなく、未病※2予防とウェルビーイング※3の鍵を握る存在です。未病の観点から見ると、皮膚のバリア機能を健全に保つことは、感染症の予防や炎症の抑制につながります。たとえば、セラミド(ヘパリン類似物質製剤:ヒルドイド®など)やヒアルロン酸を含む保湿剤の使用は、乾燥によるバリア機能の低下を防ぎ、皮膚疾患の発症リスクを軽減する効果が期待されます。
また、紫外線によるダメージを防ぐことも、皮膚がんや光老化の予防において重要です。適切なSPF・PA値を持つ日焼け止め(オキシベンゾン、パラメトキシケイ皮酸エチルヘキシルなどを含む)を継続して使用することで、長期的な皮膚の健康維持が可能となります。
さらに、皮膚のマイクロバイオーム、すなわち常在菌のバランスも重要です。ラクトバチルスなどの善玉菌を含むスキンケア製品は、皮膚の自然な免疫機能を支える新たな手段として期待されています。
ウェルビーイングとの関係も見逃せません。皮膚の状態が外見や自己肯定感に直結するため、肌トラブルはしばしばストレスや抑うつの原因になります。そのため、皮膚のケアは心の健康とも密接に関係しています。最近では、カンナビジオール(CBD)を含む軟膏やジェルが、抗炎症作用と同時にリラクゼーション効果をもたらすとして注目されています。
また、ラベンダーやカモミールなどの香りを利用したスキンケアは、感覚を通じて心を癒す手段として利用されています。さらに、ホルモンバランスの変化に伴う皮膚の変化にも対応が進んでいます。たとえば、更年期における皮膚の乾燥やたるみに対し、経皮的にエストロゲンを補充するパッチ療法(ル・エストロジェル®など)や、月経周期に合わせたスキンケア製品が提案されています。
※2:未病:明確な病名がつかないものの、体調や機能に何らかの異常や兆候が見られる状態。疾患予防の対象となる。
※3:ウェルビーイング:身体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態。単なる「健康」以上の幅広い幸福感を含む。
4. 未来の皮膚薬:個別化とテクノロジーの融合
今後の皮膚薬は、より個別化された医療と先進技術の融合によって、大きな進化を遂げると考えられます。たとえば、遺伝子治療やmRNA技術を応用したオーダーメイド治療が進行中で、水疱症などの遺伝性皮膚疾患に対する根本的な治療が期待されています。
また、スマートパッチと呼ばれるウェアラブルデバイスでは、皮膚の水分量やpH、炎症マーカーなどをリアルタイムでモニタリングし、必要な薬剤を自動で投与するシステムが研究開発されています。さらに、幹細胞を活用した再生医療の技術によって、人工皮膚の性能が飛躍的に向上しており、重度の熱傷や難治性潰瘍への応用が現実のものとなりつつあります。
加えて、マイクロバイオーム療法の進化により、特定の善玉菌を局所的に補充することで皮膚の炎症を抑える新たな治療法が登場しています。これらの動向は、皮膚薬が治療の枠を超え、予防や健康促進のツールとして機能する未来を示唆しています。
5. まとめ:皮膚薬の進化がもたらす未来

皮膚をターゲットとする薬は、今や疾患の治療だけでなく、未病の予防や心身のウェルビーイング向上といった側面からも注目されています。生物学的製剤やAI、再生医療といった先端技術との融合により、今後は一人ひとりに最適化された皮膚ケアと治療が可能になると期待されます。薬剤師としては、こうした進展を的確に把握し、患者さん一人ひとりに寄り添った情報提供を行うことが求められるでしょう。
【参考資料】
1)石河 晃・奥山 隆平・阿部 理一郎 編著『標準皮膚科学 第12版』医学書院、2025年。
2) Kamat S, Ungar B, Agarwal A, Wan J, Ross JS, Gupta R. "Innovation in Development of Dermatologic Drugs Approved by the US Food and Drug Administration between 2012 and 2022." JAMA Dermatology. 2024;160(2):226-229.
3)García-González, M., et al. "The emerging role of nanotechnology in skincare." Advances in Colloid and Interface Science, 2021;293:102437.
4)Madaan T, Doan K, Hartman A, et al. "Advances in Microbiome-Based Therapeutics for Dermatological Disorders: Current Insights and Future Directions." Experimental Dermatology. 2024;33(12):e70019.
5)一般社団法人 日本未病学会 公式サイト。
6)World Health Organization. "WHO releases updated guidance on adolescent health and well-being." 2023年。
7)薬剤師コラム くすりを知るシリーズ③未病と予防、⑤五感に作用するくすりとウエルビーイング