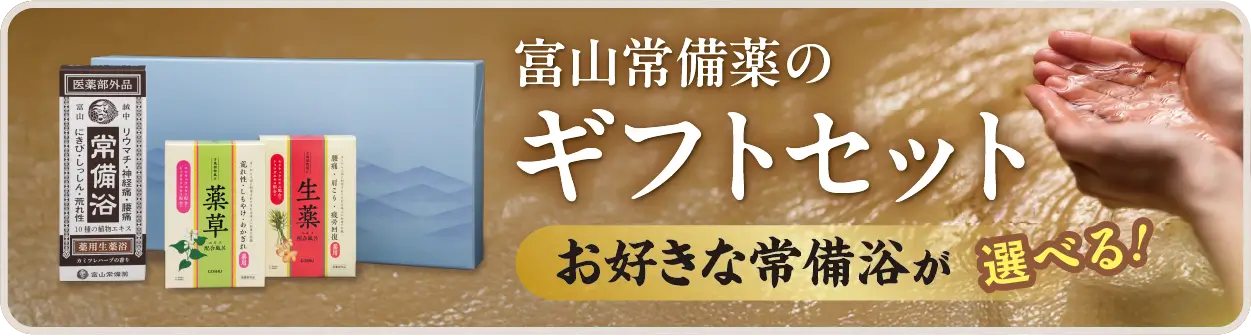富山の干し柿
富山の名産品「富山干柿」をご存じでしょうか?
江戸時代から受け継がれる伝統の味わいは、今や地元だけではなく全国からも注目を集めています。
手作業を大切にして作られる富山干柿は、濃厚な甘みと独特の食感が特徴で、お歳暮やお年賀などの贈り物としても人気です。
今回は、この富山干柿の魅力をご紹介します。

富山の名産品「富山干柿」とは
「富山干柿」は、富山県南砺(なんと)市で伝統的に作られている干し柿です。
富山干柿に使われるのは、地元の固有品種である三社柿(さんじゃがき)。
1個400gにもなる大きな渋柿で、渋みは強いものの糖度が18%以上もあり、干し柿にすると濃厚な甘みと歯ごたえが出てくることが特徴です。
富山干柿は、現在も重要な工程は人の手でおこなわれ、丁寧に作られています。
その昔ながらの豊かな風味と自然な甘みは、今なお多くの人々に愛されています。
富山干柿の歴史
富山干柿には、400年以上の歴史があります。
干し柿の製法が美濃の国(岐阜県)から伝えられたのは、慶長年間(1596~1615)とされています。
江戸時代に加賀藩3代藩主の前田利常公がその味を気に入り、生産を奨励したことで干し柿づくりが広まったと伝えられています。
医王山(いおうぜん)から吹き下ろす西風「医王おろし」が、天日干しにされた柿を揺らす光景は、地元の風物詩となっていました。
しかし、昭和に入ると農地の整備が進み、乾燥機の導入により干し柿を安定して生産する体制が整い、地元の風景も次第に変わっていきました。
風景が変わり技術が進歩しても、昔ながらの味わいはそのまま受け継がれています。
現在は富山県が推奨する「とやまブランド」や農林水産省が定める「GI登録産品」にも指定され、富山干柿の高い品質も広く評価されています。
富山干柿ができるまで

収穫された三社柿は、機械でひとつずつ皮をむき、糸でへたを縛って竹の棒に吊るされます。
酸化防止のために燻蒸したのち、天日や乾燥機で乾燥させますが、乾燥と休乾を繰り返しながら時間をかけてゆっくりと水分を抜きます。
乾燥時に欠かせない工程が「手もみ」です。
水分や糖分を柿全体に行き渡らせるために、一つひとつやさしく丁寧に柿をもむ重要な作業です。
皮むきや乾燥に機械を使うようになっても、手もみの工程は手でおこなわれています。
できあがった干し柿は検品と選別を経て個別包装され、おいしさを保った状態で出荷されます。
干し柿に渋柿を使う理由
干し柿に使われるのは、主に渋柿です。
渋柿は甘柿よりも糖度が高い一方で、渋み成分「タンニン」を多く含むことから、食べると強い渋みを感じます。
渋柿に渋みを感じるのは、タンニンが水溶性で唾液に溶けやすいためです。
しかし、乾燥させるとタンニンが水溶性から不溶性に変わります。
食べても渋みを感じることなく、柿本来の強い甘みを楽しめるようになるため、干し柿には渋柿が使われています。
ちなみに、干し柿の表面に白い粉が吹いていることがありますが、これは「柿霜(しそう)」と呼ばれるものです。
柿からにじみ出た糖分が結晶化したものなので、白い粉が多いほど甘くておいしい干し柿といえます。
干し柿の栄養
柿は、ビタミンCやカリウム、食物繊維、β-カロテンなどの栄養成分が豊富な果物です。
ビタミンCは失われやすい栄養素であり、干し柿にすると減少します。
しかし、効率的に栄養成分を摂取するなら、乾燥により成分が凝縮されている干し柿がおすすめです。
カリウムは余分な塩分を体外に排出する作用があり、体のむくみや高血圧の予防・改善に役立ちます。
食物繊維は腸内環境を整え、便通を促す効果が見込めます。
β-カロテンは強い抗酸化作用により、生活習慣病や老化の予防に効果が期待できる成分です。
また、体内で必要に応じてビタミンAに変わることで、肌や粘膜の健康維持にも力を発揮するでしょう。
栄養豊富な干し柿を生活に取り入れて、健康のサポートに活かしてはいかがでしょうか?
伝統が育む富山の干し柿の
おいしさをご賞味ください
伝統の味わいを受け継ぐ富山干柿は、現在も多くの人々に親しまれています。
400年以上の歴史をもつこの特産品は、地元の人々と自然環境が作り上げる逸品です。
新しい技術を取り入れつつ、手作業の良さも守り続けるそのおいしさを、ぜひ一度お試しください。
参照元:
とやまブランド物語 VOL.3|富山県観光・交通・地域振興局地域振興課
越中とやま食の王国|富山県農林水産部 市場戦略推進課