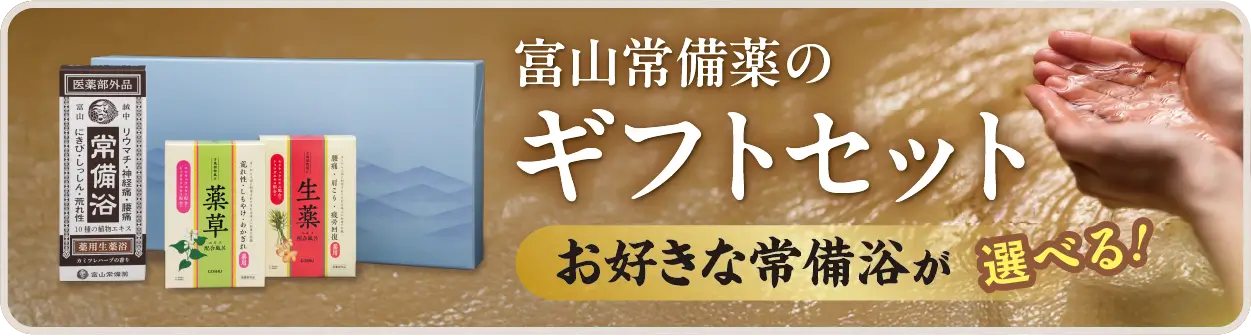夏の始まり伝える「山開き」と、現代日本人の交差地点
夏の訪れを感じ始める5月以降、日本各地で「山開き」が行われていきます。
登山道の安全祈願を願う祭事とともに、本格的な登山シーズン、夏がやってきます。山開きは単なる登山解禁行事ではなく、我々日本人と自然との関係性や、信仰心を垣間見ることができる文化的行事でもあります。今回はそんな山開きの意味と、注目したいイベントについてご紹介します。

山開きとは何か?
山開きとは、その年のシーズンの登山道が正式に開通し、夏山登山ができるとされる日のことを指します。山開きの日には、その山の登山道入り口や近隣の神社やお寺に地元関係者が集まり、山の神へ安全登山を祈願する神事が行われます。
地域や山の標高などによって具体的な日程は異なりますが、日本最高峰である富士山の場合だと、山梨県側は7月1日頃に、静岡県側は7月10日頃を予定しています。槍ヶ岳や笠ヶ岳のある北アルプスでは、岐阜県高山市の村上神社で毎年5月10日に神事が行われています。
山開きは、登山道の整備や点検が済んだことを示す意味もあり、多くの場合、山小屋の営業開始やロープウェイの稼働などもこの日に合わせて行われます。最近では、山岳遭難の防止と環境保全の観点から、啓発活動が行われることもあります。
古より伝えられてきた山への畏敬
古来より日本人は、山を神聖な領域と崇めており、『山は神のおわすところ』という認識を持っていました。故に、山そのものが御神体として信仰の対象となることも少なくありません。山開きの起源も、こうした山岳信仰と深く結びついています。
とりわけ修験道では、山は修行の場であり、神仏とのつながりを深める場とされていました。奈良県の大峰山や、岐阜・富山・石川・福井の4県にまたがる霊峰白山などでは、山伏たちが険しい山道を歩き、精神修養を行う修験の文化が今なお息づいています。
富士山もまた、かつては修験者が登る特別な山でした。女性の登山が禁じられていた時代もあり、それだけ神聖な空間と考えられていたのです。現代の山開きにも、こうした山岳信仰に基づく神事が色濃く残されており、単なる登山の解禁ではなく、自然に対する敬意と畏怖の念が込められています。
時代とともに変わる山開きの形
現代の山開きは、信仰的な意味合いを残しつつも、観光行事としての役割が大きくなっています。山開きの日には、地元観光協会や自治体が主催する記念イベントやトレッキングツアー、特産品販売などがセットで実施され、登山初心者や家族連れにも楽しめる工夫がなされています。大手のアウトドア用品メーカーも、登山道近くや麓の町に出店をすることが増えており、山開きにあわせた宿泊付きの登山イベントやグッズの配布などを行っています。
とはいえ、神事としての要素も決して薄れているわけではありません。多くの山では現在もとして地元の神職が安全を祈願し、登山者が無事に戻れるよう祝詞が捧げられています。地域によっては、登山口に神社があり、参拝してから山に入るという伝統的な所作を守って山に入る登山者も多くいます。
こうして、山開きは「観光」と「信仰」という二つの価値観が共存する、現代日本らしい行事へと変化を遂げています。自然と向き合うことに対する意味づけも、多様になってきましたが、山に対する畏敬を捨てないことが、己の身を守ることにもつながることを、今後も忘れてはいけません。
北海道最高峰旭岳「ヌプリコロカムイノミ」の魅力

北海道のちょうど中心、大雪山脈の一角をなす「旭岳」は、“カムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)”の名を冠する名峰です。巨大なカルデラ、周囲の景色をキラリと反射させる池、多種多様な高山植物などを有し、国内外から多くの登山者が訪れます。
毎年6月第3週末に山開きが行われているのですが、旭岳ではアイヌの山の祭りである“ヌプリコロカムイノミ”が行われます。この儀式では焚き火と松明、アイヌの伝統舞踊や歌に因る祈りが捧げられます。会場近くには宿泊施設も充実しているだけでなく、旭岳は山の中腹までロープウェイで登れることから、山開き以降多くの観光客で賑わうようになります。
ぜひ皆様も装備を整え、旭岳に訪れてみてはいかがでしょうか。山に対する大いなる畏敬、そして胸躍るような感動が待っていることでしょう。
旅のお供には富山常備薬の『リョウシンJV錠』を。手足のしびれ、ひざ、腰、肩などの関節痛に体の内側から飲んで効く医薬品です。1日1回、食前食後問わず、いつでもお好きなタイミングでお飲みいただけるため、変則的なスケジュールになりがちな旅先でもご愛用いただけます。いくつになっても軽やかな足取りで、素敵な日々をお過ごしください。
この記事で紹介した商品