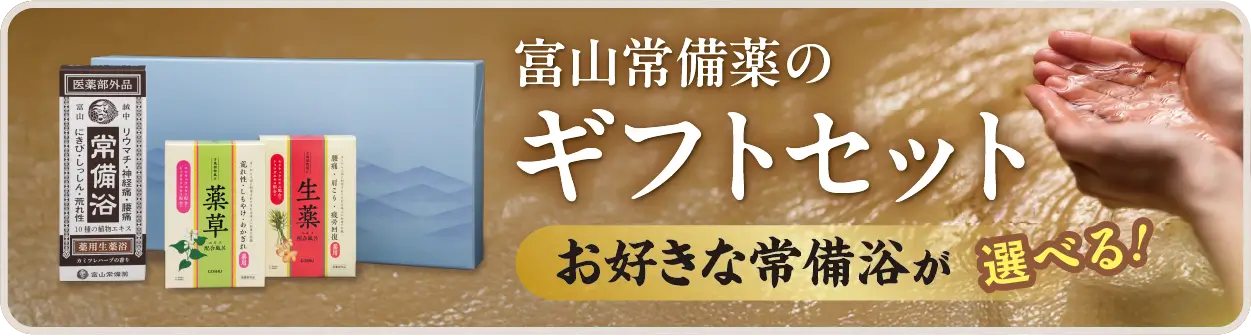超高齢社会を元気に乗り切る!
「未病」と「セルフメディケーション」で守る、あなたの骨と関節
~くすりを知るシリーズ⑮~
薬剤師 NK
はじめに
日本は世界に先駆けて超高齢社会を迎えており、健康寿命の延伸は喫緊の社会課題となっています。
特に骨や関節の健康は、移動能力や日常生活の自立に直結するため、QOL(生活の質)の維持において重要なテーマです。加齢によって骨密度が低下しやすくなり、関節の軟骨がすり減ることで痛みや可動域の制限が生じます。これらは必ずしも「病気」として明確に診断されるわけではなく、いわゆる「未病」の状態であることも多く、早期の対応が求められます。
今回は、未病およびセルフメディケーションの視点から、骨と関節軟骨をターゲットとする医薬品・保健機能食品の活用方法について紹介し、健康寿命延伸の可能性を考えてみましょう。
1. 骨と関節の変化を捉える:未病の視点から
骨は20代をピークに徐々に骨密度が低下し、特に閉経後の女性では女性ホルモン(エストロゲン)の減少により急激に骨量が減少します。骨粗鬆症の前段階では「骨量減少」としてとらえられ、骨折のリスクが高まる兆候とされています。
同様に、関節軟骨も加齢とともに摩耗し、関節の滑らかな動きが失われ始めます。未病の段階で骨密度や関節の柔軟性を保つためには、早期の栄養補給や運動習慣の見直しが鍵となります。

「未病」って何?
「未病」とは、まだ病気ではないけれど、少しずつ病気に向かっている状態のこと。「健康」と「病気」のちょうど間くらい、と考えると分かりやすいかもしれません。骨や関節のトラブルも、実はこの「未病」の段階から始まっていることが多いんです。
•骨のサイン: 例えば、骨の密度が少しずつ低下してきているのに、あなたは全く気づかないかもしれません。でも、この「骨密度が低下している状態」が、将来の骨粗鬆症につながる「未病」なんです。特に、若い女性で無理なダイエットをしていると、骨を作る材料が不足し、将来の骨の健康に影響が出ることもあります。
•関節のサイン: 関節も同じです。膝や股関節にちょっとした違和感があったり、軽い痛みを感じたりしたことはありませんか?これも、本格的な変形性関節症になる前の「未病」のサインかもしれません。軟骨が少しずつすり減り始めているサインの場合もあります。
病気がはっきりする前に、この「未病」の段階で「何かおかしいな?」と気づき、対策を始めることが、とても重要なんです。早くからケアを始めることで、病気の発症を遅らせたり、症状がひどくなるのを防いだりできる可能性が高まります。
「未病」の段階でできることは、こんなことがあります。
•「あれ?骨密度、少し低いって言われたな…」と思ったら、放っておかないで対策を始めること。
•「最近、膝がちょっときしむ感じがするな…」と感じたら、軽い運動を試したり、栄養を補うことを検討したりすること。
•「健康的な生活をしてるかな?」と自分の生活習慣を見直すこと。運動不足や栄養の偏り、タバコ、お酒の飲みすぎなどは、骨や関節にとって良くありません。
さあ、健康寿命を延ばすために、まずは「未病」のサインを見逃さないようにしましょう!
骨粗鬆症や変形性関節症は、進行するまで明確な症状が現れにくく、未病の段階で介入することで、将来的な骨折や慢性痛を予防できる可能性があります。骨粗鬆症は骨密度の低下によって骨がもろくなる病態で、特に閉経後女性や高齢者で顕著です。
変形性関節症は、関節の軟骨がすり減ることで関節の変形や痛みを引き起こします。
いずれも初期段階では自覚症状に乏しいため、健康診断や地域の骨密度測定会などで異常を早期に見つけ、生活習慣の改善やセルフケアに結びつけることが重要です。
2. セルフメディケーションの実践:市販薬とサプリメントの活用
骨や関節の健康を維持するためのサプリメントやOTC医薬品は、セルフメディケーションの第一歩として非常に有効です。以下は代表的な製品とその成分の特徴です。
- 骨密度の維持をサポートするサプリメント
・「マルチミネラル」(ファンケル):体内では合成できない必須ミネラルは健康に欠かせない栄養素で、1日に必要な量の半分を手軽に補えます。吸収されにくいカルシウムのためには、納豆のネバネバ成分「ポリグルタミン酸」を配合しています。
・「ディアナチュラスタイルカルシウム・マグネシウム・葉酸・ビタミンD」(アサヒ):骨や歯の形成に必要な栄養素のカルシウムとマグネシウムに加えて、亜鉛とカルシウムの吸収をサポートするビタミンDを配合しています。
- 関節の柔軟性維持に役立つ成分
・「ひざサポートコラーゲン」(キューサイ):機能性関与成分のコラーゲンペプチドが配合されており、膝の曲げ伸ばし改善傾向を示します。
・「グルコサミンEX」(アサヒ):機能性関与成分のグルコサミン、コンドロイチン、ケルセチンを配合し、ダブル軟骨成分といたわり成分の3成分の組み合わせにより、移動時のひざ関節の悩みを改善します。
- 外用鎮痛薬
・「ボルタレンEXテープ」(同仁医薬化工)、「フェイタスZαジクサス」(久光製薬):外用鎮痛消炎剤として局所の炎症や痛みを和らげます。
これらの市販品は未病の段階や軽度の症状に対してセルフケアを行う上で重要な役割を果たしますが、過剰摂取や他の薬との相互作用には注意が必要です。継続的に使用する場合は、薬剤師や医師に相談しましょう。
3. 医療用医薬品による予防と治療
骨粗鬆症の治療には以下のような医療用医薬品が用いられています。
・「アレンドロン酸」(フォサマック、ボナロン):ビスホスホネート製剤で、骨吸収を抑制し骨密度を改善します。週1回の投与で効果が期待され、副作用として消化器症状に注意が必要です。
・「ラロキシフェン」(エビスタ):選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)で、骨にはエストロゲン様の作用を示しながら、乳腺や子宮には影響を与えにくいのが特徴です。閉経後女性に適応があります。
・「テリパラチド」(テリボン、フォルテオ):副甲状腺ホルモン製剤で骨形成を促進する作用があります。特に骨折リスクが高い重症例に使用されます。
・「デノスマブ」(プラリア):抗RANKL抗体で破骨細胞の活性化を抑制し、骨吸収を防ぎます。半年ごとの皮下注射で長期的な効果が期待されます。
関節症に対しては以下のような薬剤があります。
・「セレコキシブ」(セレコックス):選択的COX-2阻害薬で、消化器への副作用を軽減しつつ炎症と痛みを抑える非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)です。
・「ヒアルロン酸関節注射」(アルツ、スベニール):関節内に注射し、潤滑性を回復させ、疼痛軽減を図ります。変形性膝関節症の治療によく用いられます。
・生物学的製剤(アダリムマブ(ヒュミラ)、トシリズマブ(アクテムラ)など):関節リウマチや重度の関節炎に用いられ、炎症性サイトカインを標的として関節破壊を防ぎます。
これらの薬剤は、症状の進行を防ぐとともに、QOLの改善を目的とした治療に用いられます。患者の症状や背景に応じた適切な薬剤選択が重要です。
4. 関節軟骨の再生と再生医療の可能性
関節軟骨は血流を持たず、再生能力が極めて低い組織です。 従来は進行を遅らせる対症療法が中心でしたが、近年では再生医療が注目されています。自己幹細胞を用いた軟骨再生や、iPS細胞から分化させた軟骨細胞による修復療法などが研究・臨床応用されています。
1. 自家培養軟骨細胞移植術(ACI)
患者自身の軟骨細胞を培養して患部に移植する技術。スポーツ選手の治療などで活用され始めています。
2. 間葉系幹細胞(MSC)を用いた治療
幹細胞が損傷部に分化・分泌因子を出すことで、軟骨修復を助けるとされる治療法。
3. ヒアルロン酸・PRP(多血小板血漿)療法
軟骨保護・修復促進の補助として使われるが、確定的な再生効果はまだ限定的。
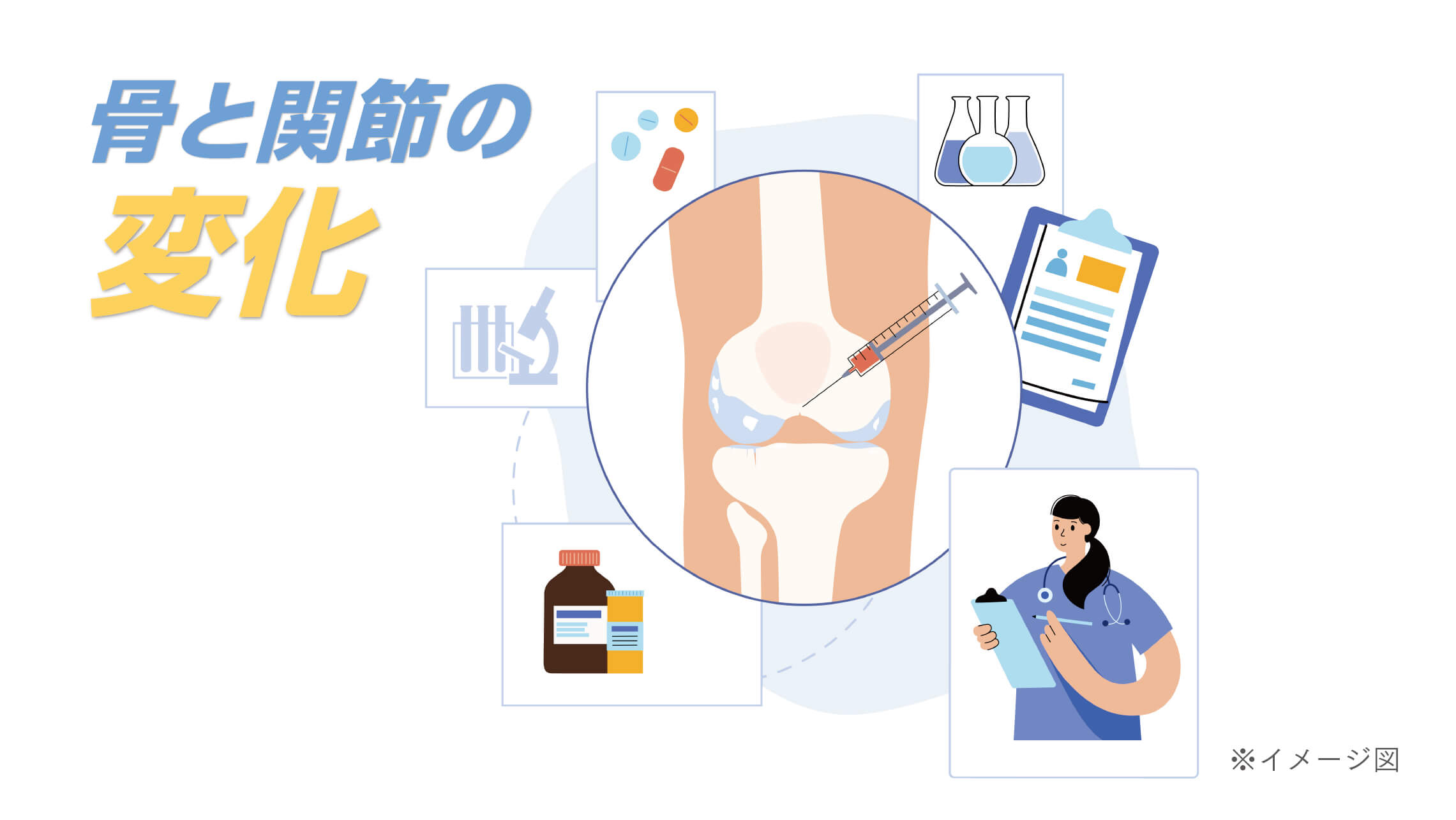
おわりに
「骨や関節の未病対策とセルフメディケーションは、生活の質を高めるために非常に重要です。市販薬や医療用医薬品を適切に使い分け、早期からの対策を講じることで、寝たきりや介護状態の予防につながります。薬剤の選択肢が広がる中、正しい情報を持ち、自らの健康を管理し、健康寿命を延ばす意識が今後ますます求められるでしょう。
【参考資料】
1. 厚生労働省.「健康日本21(第二次)」
2. 日本骨粗鬆症学会. 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版.
3. 日本整形外科学会. 変形性関節症診療ガイドライン2023.
4. 日本薬剤師会. セルフメディケーションについて.
5. 各製品の添付文書・製品紹介資料より引用。
6. 首相官邸ホームページ. 再生医療の現状と展望.(2021年)
7. Yamasaki T. et. Al. 関節リウマチにおける生物学的製剤. 就実大学薬学雑誌 2020, 7, 10-18.