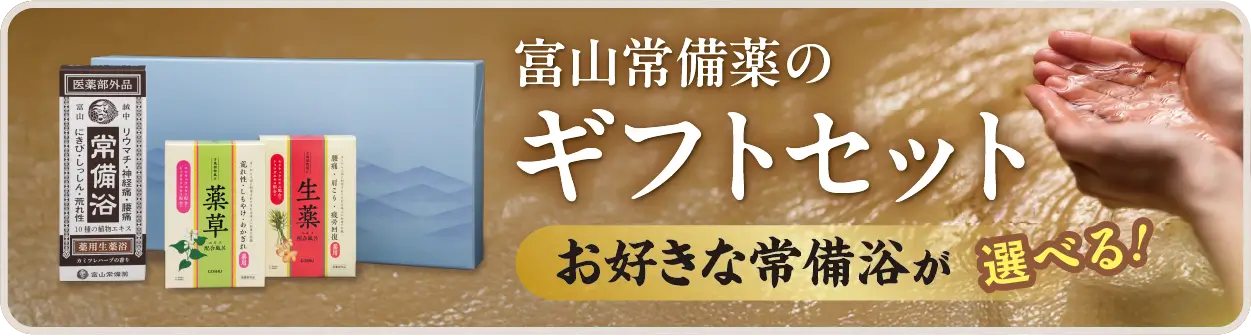医薬品が出来るまで
薬剤師 Kira
医薬品には、大きく分けて「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。
では「医療用医薬品」が「新薬」として開発されるまでには一体どれ位の時間や費用がかかるのでしょうか。
「製薬協ガイド2023」によると、日本において1つの「新薬」を開発するには約9年から16年の期間と多額な費用が掛かります。(2013年医薬産業政策研究所のアンケートによる実態調査では、552億円と報告。)実際に「新薬」の成功率は約25,000分の1しかありません。
ここで、「新薬」開発のステップをご紹介します。
STEP1「基礎研究(2~3年)」

将来「薬」となる可能性のある新しい物質(成分)の発見や、化学的に創り出すための研究から始まります。「薬」のモトは、植物や微生物などの天然素材から発見したり、科学技術を使ってつくり出したりしています。
STEP2 「非臨床試験(3~5年)」

「薬」として可能性のある物質を、動物や培養細胞を用いて試験し、有効性と安全性を研究します。また、「薬」のモトの吸収・分布・代謝・排泄の過程や、品質・安定性に関する試験も行います。
STEP3「臨床試験(治験)(3~7年)」

臨床試験とは、ヒトを対象とした有効性と安全性のテストのことで、「治験」とも呼ばれます。非臨床試験を通過した「薬」の候補(治験薬)が、安全で実際にヒトに効果があるかどうかを調べる最終的な確認が臨床試験(治験)です。
治験は下記の3段階に分かれ、病院などの医療機関で、健康な人や患者さんを対象に同意を得たうえで行われます。
第1相試験(フェーズⅠ)
少数の健康な人を対象に、副作用などの安全性について確認します。
第2相試験(フェーズⅡ)
少数の患者さんを対象に有効で安全な投与量・投与方法などを確認します。
第3相試験(フェーズⅢ)
多数の患者さんを対象に有効性と安全性について今まで使われてきた基準となる「対象薬」などとの比較試験行い、「対象薬」よりも優れているかを確認します。
このフェーズⅢで「薬」としての有用性があると判断された場合に、開発企業は「承認申請」を行います。
STEP4「承認申請と審査」

開発企業は有効性・安全性・品質などが証明されたあとに、厚生労働省に新薬として製造・販売するための承認・許可がもらえるように申請します。そのあと、学識経験者などで構成する薬事・食品衛生審議会などの審査を受け、「薬」として製造・販売が認められると、薬価算定され発売することが出来ます。

(参考)