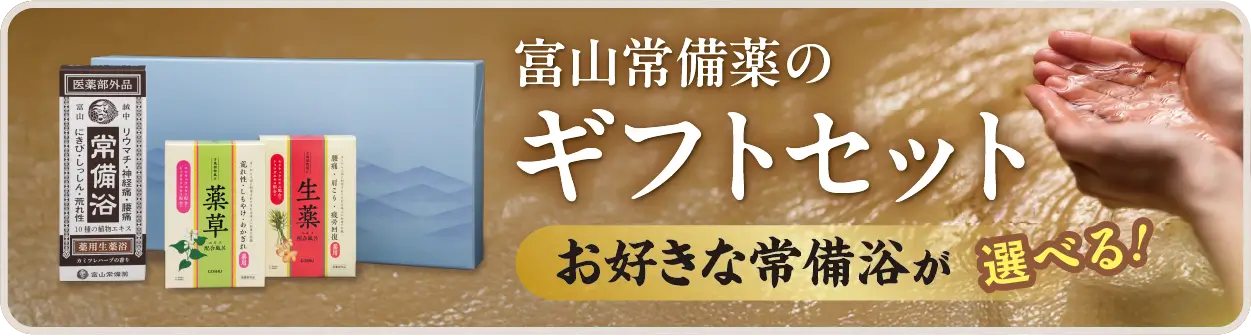夏を乗り切る水分補給術!
正しい知識と習慣で暑さに強くなる
日差しの強い夏の季節、「水分をこまめにとりましょう」という言葉を頻繁に目にします。けれども、いつ、何を、どうやって飲むのが効果的なのかをしっかり理解している人は、意外と少ないのではないでしょうか。水分補給の基本を誤ると、熱中症や体調不良のリスクが高まることもあります。
本記事では、水分補給の重要性やおすすめの飲み物、食事との関係、そして注意すべきポイントまで、暑さを健康的に乗り切るための知識をご紹介します。

水分補給の基本とその重要性
私たちの体の約60%は水分で構成されています。夏場は汗によって多くの水分が体外に排出されるため、日常生活においてもこまめな補給が欠かせません。特に高齢者や子どもは体内の水分量が少なく、脱水に気づきにくいため、より注意が必要です。
厚生労働省の「熱中症予防のための情報・資料」でも、「喉の渇きを感じる前からの補給」が強く推奨されており、気温や湿度が高い日、屋外活動時だけでなく、室内でも注意が必要とされています。水分補給は、体温調整や血流の維持、代謝の促進など、生命活動を支える基本的な行動です。暑い時期こそ、意識的な補給が大切です。
何を飲むべき? シーン別・おすすめの飲み物
水分補給といっても、ただ水を飲めばよいというわけではありません。シチュエーションによって、適した飲み物を選ぶことが重要です。
たとえば、運動や屋外での作業など大量に汗をかく場面では、ナトリウムや糖分を含むスポーツドリンクや経口補水液が適しています。厚生労働省は、熱中症予防のために「ナトリウムを40〜80mg/100mL程度含む飲料」が望ましいとしています。こうした飲料は、体内の電解質バランスを保ちながら、効果的に水分を吸収するのに役立ちます。
一方で、日常的な水分補給には、常温の水や麦茶、ルイボスティーなどカフェインを含まない飲み物が適しています。カフェインは利尿作用があるため、水分を体内に留めたい時期には控えめにするのが望ましいでしょう。
食事からとる「食べる水分」も味方に
水分は飲み物だけからとるものではありません。実は食事にも多く含まれており、日々の食生活も重要な水分補給源になります。夏野菜であるきゅうりやトマト、果物のスイカや桃などは水分含有量が非常に高く、栄養と同時に水分をとれる優れた食材です。
汁物や味噌汁も、ナトリウムと水分をバランスよく摂取できるため、夏の食卓には欠かせません。特に食欲が落ちやすい季節には、冷製スープや酢の物など、のど越しの良い料理で無理なく水分を補いましょう。
食事をきちんととることは、夏バテ対策にも効果的です。飲み物だけから水分を摂るのにも限界がありますから、上手に組み合わせていきたいですね。
実は危険?水分補給の落とし穴
「飲んでいるつもり」でも、選び方や飲み方を誤れば逆効果になることもあります。代表的なのがアルコール。ビールなど冷たいアルコール飲料は、一見水分補給になりそうですが、実際には利尿作用が強く、体内の水分を奪ってしまうため、脱水を引き起こすリスクが高まります。厚生労働省も、アルコール飲料は「水分補給としては不適切」との見解を示しています。
ちなみに、ビール10本で11本分の尿量になるといい、むしろ脱水の原因になり得ます。特に夏はバーベキューやビアガーデンなど、アルコールを摂取する機会も増えますから、気を付けたいところです。
また、コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲料も、過剰に摂取すると利尿作用によって水分が排出されてしまいます。冷たすぎる飲料の一気飲みも、胃腸に負担をかけたり、体を冷やしすぎたりする原因になるため、常温に近い飲み物を、こまめに少しずつ摂る習慣が望ましいのです。
今を知り、未来を守る選択を

水分補給は、暑さ対策の基本であり、命を守る行動でもあります。公的機関の示すデータや注意喚起をもとに、飲む量・タイミング・飲み物の選び方を少し意識するだけで、熱中症や体調不良の予防につながります。
水分を「とる」のではなく、「うまくとる」こと。日々のちょっとした心がけが、夏をより快適に、健康的に過ごす鍵となるでしょう。ご自身はもちろんのこと、ぜひ周囲の方にも注意喚起ください。健康で楽しい夏を過ごしましょう。
富山常備薬では『リョウシン長命青汁』をご案内しています。「大麦若葉」をベースに「長命草」をブレンドし、乳酸菌500億個(1包あたり)と82種類の野菜果物発酵エキスをプラス。ごくごく飲める美味しさと豊富な栄養の両方を実現した、夏にぴったりの青汁です。水分補給の際にぜひお召し上がりください。
この記事で紹介した商品